ランプの種類
色彩検定2級トピック色彩検定では、普通の電球から普段日常では使わないような照明まで、様々な光源器具が紹介されています。一つ一つ個別覚えていくのは大変なので、必ず分類を最初に確認してから、細かく掘り下げていきます。
あと、分光分布が出てきます。苦手な人も多いかと思いますが、頑張って見ていきましょう。スペクトラム色を入れない白黒にしていますので、形に注目しましょう。
まず、光源の種類は大きく2つに分かれます。
- 熱放射発光
- ルミネセンス
「熱放射発光」は、白熱電球のように熱放射、つまり物を加熱することで光る現象を利用した光源です。「色温度」のトピックをまだ勉強していない人は、先にそちらを見るとわかりやすいかもしれません。物体は高温で加熱していくと発光を始め、徐々に赤くなり、白くなり、そして青くなります。この高温で白く発光している状態が「白熱」ですね。試合がエキサイトしていることを「白熱している」なんてい言いますが白い光を出すほど高温なわけです。熱放射発光は、「白熱電球」と「ハロゲン電球」の2つの「白熱ランプ」をが出て来ます。
【白熱ランプ】
- 白熱電球
- ハロゲン電球
一方でルミネセンスは、熱放射以外の発光です。放電発光や電界発光(エレクトロルミネセンス)などがありますが、ここでは「熱放射以外」でざっくり捉えましょう。色彩検定関係ない、どっか別のところで説明を入れます。こちらは様々な色の「蛍光ランプ」「HIDランプ(高輝度放電ランプ)」「LED」が登場します。
① 白熱ランプ

白熱電球

ハロゲン電球
【白熱電球】
いわゆる電球です。
特徴
- 色温度は約 2800 K
- 演色評価数の基準光に近い(演出性が高い)
- 自由に光の量の調整ができる
分光分布はめちゃくちゃわかりやすいですね。一瞬で覚えられます。
【ハロゲン電球】
白熱電球と仕組みは同じですが、中にハロゲンガスが入っているので、白熱電球より明るく高寿命です。
特徴
- 小型で明るく演出性が高い
- 白熱電球より長寿命
- 白熱電球より長波長が抑えられている
ハロゲン電球の分光分布は
白熱電球から長波長を削ったもの
と覚えておきましょう。
② 蛍光ランプ

特徴
- 寿命が長く消費電力が小さい
- 色温度や演色性によって様々なタイプがある
3種類の蛍光ランプの分光分布を見ておきましょう。
普通形
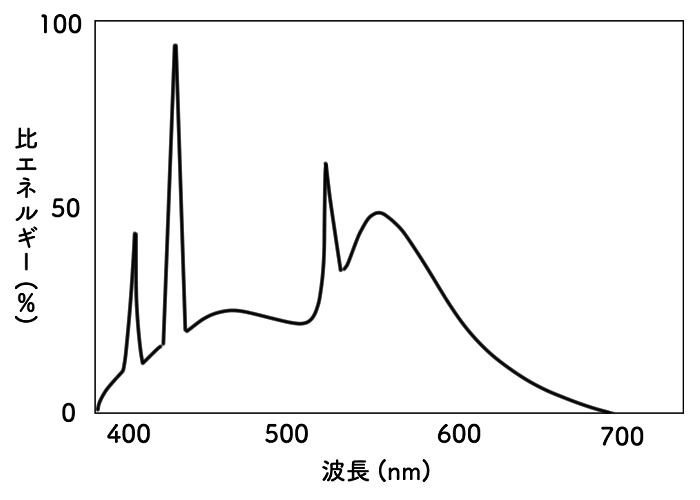
高演色形
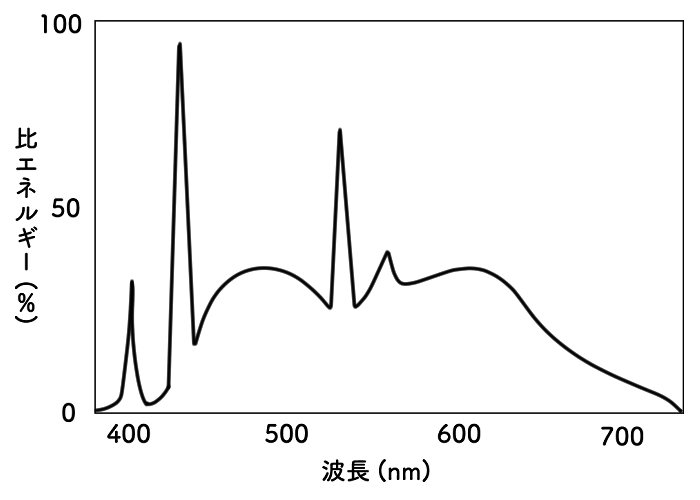
3波長域発光形
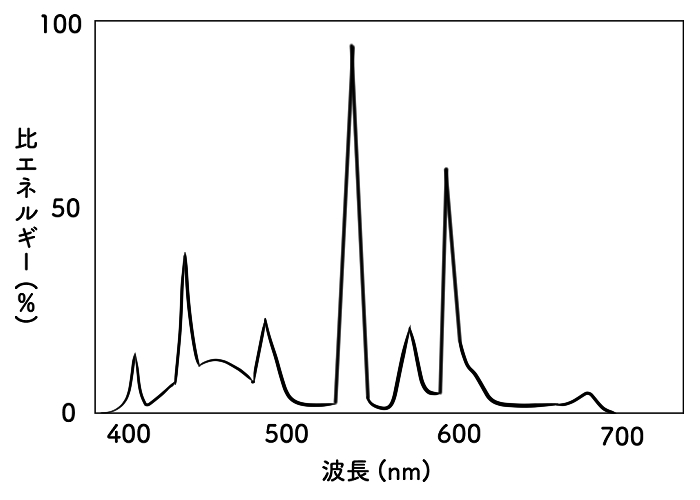
「普通形」の分光分布は、B(450nmくらい)とG(550nmくらい)にツノがあります。しかし、Rの波長は激減しています。波長のバランスが良くないので、見える色が少し変わってしまう(演色性がよくない)ですね。
一方、「高演色形」は「普通形」と似ているものの、Rの波長が増強されています。また「3波長域発光形」はRGBそれぞれにツノを作ってあげて各波長を補強しています。逆にそれ以外は抑えめにして省電力にする、という完全な割り切りようです。
③ HIDランプ
メタルハライドランプ

特徴
- 明るく経済的で演出性がよく、大光量
- 様々な色温度のものがある
水銀ランプ

特徴
- 白熱電球の約3倍の発光効率
- 演色性は悪いが寿命が長く経済性が良い
高圧ナトリウムランプ

特徴
- 寿命が白熱電球の4~9倍
- 明るさが白熱電球の3~4倍
- 演出性に優れ、白色電球ににた色温度
低圧ナトリウムランプ

特徴
- オレンジ系の単光色で演色性が悪い
- 高圧ナトリウムランプや蛍光ランプなどに置き換えられた
④ LED
LEDこと発光ダイオードは、いまやお馴染みのランプですね。1993年に高輝度青色ダイオードが発明、量産化されたことで、一気に実用化が進みました。この実用レベルの青色LEDの発明で中村修二先氏がノーベル化学賞を取得しましたね。(そしてあれこれ特許でもめてました)いずれにせよ、日本人が生み出した世界を変えた発明の一つです。
LEDは、とてもシンプルかつ優秀な特徴を持ちます。
- 発熱が少なく紫外線赤外線がほとんどない
(デリケートな展示物等にも使える) - 寿命が数万時間
(蛍光ランプが1万数千時間)